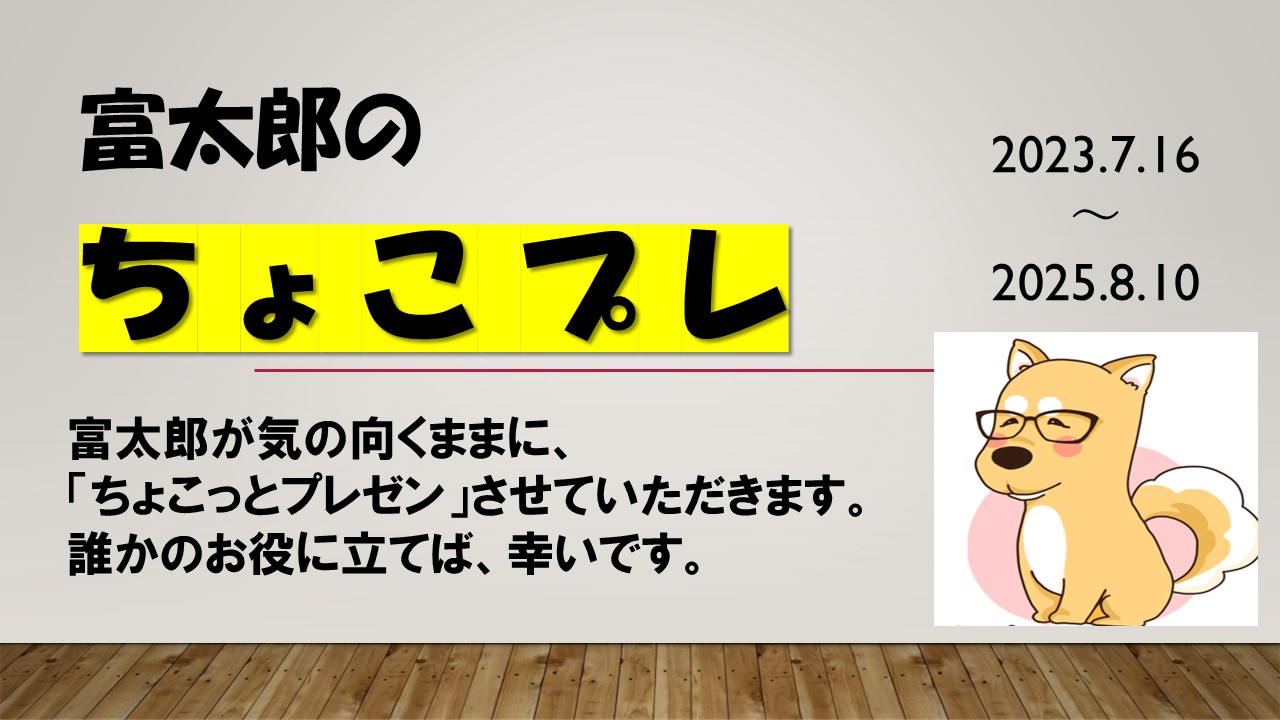
★ 2023年7月から2025年8月まで、『ココナラ』のブログに投稿した内容です。
順次、追記していく予定です。
今回のお題「所有者不明土地管理命令」 2024.10.27
不動産の所有者が、調査を尽くしても知ることができなかったり、又はその
所在を知ることができない場合、当該不動産の管理や処分が困難になります。
公共工事の用地取得や空き家の管理など、所有者の所在が不明なケースで
は、従来はその属性等に応じて「不在者財産管理人」や「相続財産管理人」な
どの『財産管理制度』が活用されてきました。
しかし従来の『財産管理制度』は、対象者の『財産全般』を管理する仕組み
となっていることから、非効率になりがちで、利用者の負担が大きいでした。
また、所有者をまったく特定できない不動産については、既存の『財産管理
制度』を利用することができないという問題点がありました。
そこで、令和3年の民法改正により「特定の土地又は建物のみ」に特化して
管理を行う『所有者不明土地管理制度(民法264条の2~264の7)』及び『所有
者不明建物管理制度(264条の8)』が創設され、土地・建物の効率的かつ適切
な管理を実現し、所有者が特定できないケースにも対応が可能になりました。
「所在者不明土地」を例に、ポイントをあげます。
(1) 裁判所の管理命令 (要件)
① 利害関係人の請求があること
② 所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地
(建物)であること
③ 管理の必要が認められること
④ 裁判所が所定の事項を公告し、公告から一定の期間内に当該土地(建物)
の所有者から異議の届出がないこと
なお、裁判所の管理命令の効力は、対象の土地にある動産(土地所有者の所
有するもの)にも及びます。
(2) 管理不全土地(建物)管理人
① 裁判所は、「所在不明土地(建物)管理命令」において、『所有者不明土
地(建物)管理人』を選任します。
② 管理人に土地(建物)その他の物の「管理処分権」が専属します。
= 所有者は、「管理処分権」を失います。
③ 管理人は、「保存行為」及び「性質を変えない範囲内における利用改良
行為」の範囲を超える行為 [例:売却等の土地(建物)の処分] を行うには、
裁判所の許可を得ることが必要です。
④ 管財人には『善良なる管理者(善管)注意義務』があります。
富太郎の家の近所に、立地は良いのに、20年以上にわたって空き家だった
ビルがりましたが、ここ2年ほどで新しいビルに建て替わりました。
この法律ができたことによるものかは判らないものの、可能性はかなり高い
と考えています。
次回は「所有者は判明しているが、不動産が適切に管理されていないケース
について、説明させていただく予定です。
今回は、以上です。
今回のお題「管理不全土地管理命令」 2024.11.3
前回のお題「所在不明土地(建物)管理命令」が発せられるのは、不動産の
所有者が、調査を尽くしても知ることができなかったり、又はその所在を知る
ことができない場合でした。
一方、不動産の所有者が判明している場合でも、所有者による管理が適切に
行われず、荒廃・老朽化によって危険を生じ管理不全状態にある土地・建物
は、近隣に悪影響を与えることがあります。
このような危険な管理不全状態にある不動産については、従前から「物権的
請求権」や「不法行為に基づく損害賠償請求権」等の権利に基づき、『訴えを
提起して判決を取得し、強制執行をする』ことによって対応が行われてきました。
しかし、管理不全状態にある『不動産の所有者に代わって管理を行う者を選
任する仕組み』が存在しなかったことから、管理不全状態にある不動産につい
て『継続的な管理』を行うことができず、実際の状態を踏まえて適切な管理措
置を講ずることが困難であるという問題がありました。
そこで、令和3年の民法改正により、管理不全状態にある土地・建物につい
て、利害関係人からの請求に基づき、裁判所が管理人による管理を命ずる処分
を可能とする『管理不全土地・建物管理制度(民法264条の9~264条の14)』が創設され、管理人
を通じて適切な管理を行い、「管理不全状態を解消」する
ことが可能となりました。
「管理不全土地」を例に、ポイントをあげます。
[ ]内は、前回取り上げた「所有者不明土地」のケースです。
(1) 裁判所の管理命令 (要件)
① 利害関係人の請求があること [同]
② 所有者による土地(建物)の管理が不適当であることによって他人の
権利又は法律上保護される利益が侵害され、または侵害されるおそれが
あること
[所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地
(建物)であること]
③ 管理の必要が認められること [同]
④ 裁判所が当該土地(建物)の所有者の陳述を聴くこと
[裁判所が所定の事項を公告し、公告から一定の期間内に当該土地
(建物)の所有者から異議の届出がないこと]
なお、裁判所の管理命令の効力は、対象の土地にある動産(土地所有者の所
有するもの)にも及びます。 [同]
(2) 管理不全土地(建物)管理人
① 裁判所は、「管理不全土地(建物)管理命令」において、『管理不全土
地(建物)管理人』を選任します。 [同]
② 管理人に土地(建物)その他の物の「管理処分権」が有します。
⇒ 所有者は、「管理処分権」を失いません。
[管理人に土地(建物)その他の物の「管理処分権」が専属します。
= 所有者は、「管理処分権」を失います。]
③ 管理人は、「保存行為」及び「性質を変えない範囲内における利用改良
行為」の範囲を超える行為 [例:売却等の土地(建物)の処分] を行うには、
裁判所の許可を得ることが必要です。 [同]
裁判所は、許可をするときには、所有者の同意が必要です。
[所有者の同意は不要(所在不明なので、同意の取りようがない)]
④ 管財人には『善良なる管理者(善管)注意義務』があります。
ごみ屋敷問題や、過疎地域の相続問題等の解決に活用されることが期待
されます。
今回は、以上です。
今回のお題「共同親権を認める法改正」 2024.11.10
父母の離婚が、子の養育に対して深刻な影響を及ぼしていると言われます。
従来は、離婚後は父または母のどちらかが単独で親権者になることとされて
おり、離婚後に共同親権とすることは認められていませんでした。
それが、令和6年5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」の
成立により、離婚後に共同親権を選択できるようになりました。
具体的には、協議上の離婚の場合には、その協議で、その双方または一方を
親権者と定めることとし(改正民法819条1項)、裁判上の離婚の場合には、
裁判所が父母の双方または一方を親権者と定めることとする(改正民法819条
2項)ことにより、離婚後も父母が共同で親権を行使できるようにしました。
婚姻中は共同親権ですが、離婚後においては単独親権か共同親権かを選択
できるようになったわけです。(共同親権が強制されるわけではありません。)
ただし、父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には、単独
親権としなければならないとされています。(改正民法819条7項)
例えば、一方の親から子への虐待の恐れがあるようなケースには、子の利益
を守るために、共同親権の選択に制限を設けたわけです。
また、同時に子の権利を確保するため、親の責務等の規定が新設され、その
内容が明確化されました。
改正民法817条の12 【親の責務等】
父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するととも
に、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、
かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなけれ
ばならない。
2 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の
履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなら
ない。
なお、この改正は、公布の日(令和6年5月24日)から起算して2年を超えない
範囲内において政令で定める日に施行されることとなっています。
昨今、子供絡みの悲しい事件が多すぎる気がします。 今回の民法改正で
悲しい思いをする子供が一人でも多く減ることを希望してやみません。
今回は、以上です。
今回のお題「教唆犯・共同正犯」 2024.11.17
昨今、指示役の指示に基づいて、知らない者同士が民家に押し入る強盗事件
が頻発しています。 実行犯は、指示役に脅されて犯行に及んだとの報道も。
『教唆犯』とは、「人を教唆して犯罪を実行させた者」(刑法61条1項)であ
り、教唆犯が成立するためには、①他人に犯罪の決意を生じさせる「故意的
教唆行為」と、②それによって正犯者が犯罪の実行に出たこと、の二つの要件
が必要とされています。
そして『教唆犯』には、正犯の刑が科されます(刑法61条1項)。正犯の法定
刑の範囲内で刑を科すということであり、実際の正犯者より重い刑でもかまい
ません。
司法書士試験の過去問 平成2-25-(5)
問 医師が、看護師を指示して患者に毒薬を投与して、患者を殺害した場合に
は、看護師が毒薬であることを知らなくても、医師については、殺人罪の
教唆犯が成立する。
答 × 看護師は毒薬であることを知らないのであるから、看護師には殺人罪
の構成要件的「故意」が欠ける以上、正犯者とはいえず、医師には殺人罪の
教唆犯は成立せず、構成要件的故意を欠く者を(あたかも道具のように)利用
する『間接正犯』を認めるのが判例・通説であり、医師には『殺人罪の間接
正犯』が認められる。
司法書士試験の過去問 昭和62-24-(1)
問 13歳の児童に指示して他人の財物を盗み出させたときは、当該児童に対
し、暴行、脅迫等その意思を抑圧する手段を用いたと否とを問わず、間接正
犯による窃盗が成立する。
答 × 実行行為に出たものについて是非弁別能力が認められるときでも、常
に教唆犯が成立するわけではなく、暴行、脅迫等意思を抑圧するような手段
を用いることにより、被利用者を道具と評価できる場合、利用者には間接正
犯が成立し得る。 この点につき判例(最判昭58.9.21)も、日頃顔面にタバ
コの火を押し付けるなどして自己の意のままにしてきた12歳の養女に窃盗
を行わせたという事例において、「自己の日頃の言動に畏怖し意思を抑制さ
れている同女を利用して右窃盗を行ったのであるから、たとえ同女が是非弁
別能力を有するとしても、間接正犯が成立する」と判示している。(「意思
を制圧する手段を用いたと否とを問わず」とする点で誤り。)
司法書士試験の過去問 平成22-24-(う)
問 Aは、生活費欲しさから、中学1年生の息子Bに包丁を渡して強盗をして
くるよう指示したところ、Bは嫌がることなくその指示に従って強盗するこ
とを決意し、コンビニエンスストアの店員にその包丁を突き付けた上、自己
の判断でその場にあったハンマーで同人を殴打するなどしてその反抗を抑圧
して現金を奪い、Aに全額渡した。この場合、強盗(既遂)罪の共同正犯が成
立する。
答 まず、親Aは刑事未成年者である息子Bに強盗を指示して実行させている
ものの、Bは指示に嫌がることなく自己の判断で強盗を実行していることか
ら、AがBの意思を抑圧しているものとはいえず、Aに強盗罪の間接正犯は
成立しない。また、Aは生活費欲しさから包丁を与えた上でBに強盗を指示
し、Bが奪った現金をすべて受け取っていることから、Aには正犯性が認め
られ、『教唆犯』ではなく、『正共同犯』が成立する。(最決平13.10.25)
「『共同正犯』とは、「二人以上共同して犯罪を実行することをいう。」
(刑法60条)
刑法60条は、共同正犯者は「すべて正犯とする」と規定しており、犯罪を
実行するための行為の一部を行えば、現実に生じた犯罪的結果の全部の責任を
課されることになります(一部実行全部責任の原則)。
では、「強盗を指示したら、実行役が相手を殺してしまったらどうなるか。」
については、次回の お題 にする予定です。
今回は、以上です。
今回のお題「結果的加重犯」 2024.11.24
例えば、AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう『教唆』した
ところ、Bは甲宅に侵入して金品を物色したが、その最中に甲に発見されたの
で、甲に刃物を突き付けて甲から金品を強取した。というケースで、Aには、
「住居侵入・強盗罪」の『教唆犯』は、成立するでしょうか?
判例は、「窃盗」を教唆したところ、被教唆者が「強盗」をした場合には、
教唆者には軽い「窃盗罪」の範囲において『教唆犯』が成立すると判示しまし
た(最判昭25.7.11)。
「教唆」(あるいは「共謀」、「共犯」、「幇助」)で、教唆の内容よりも、
被教唆者(共謀者、正犯者)が「重い犯罪」を実行した場合(共犯の過剰)に、
教唆者には、「教唆者の故意」と「被教唆者の犯した犯罪」の構成要件(犯罪
のとして法の条文に定めらた内容にあてはまっていること)が実質的に重なり
合う範囲で、軽い犯罪の教唆が成立します。
●教唆したのは「窃盗」、実際に起きたのは「強盗」。犯罪類型の似ている
場合は「軽いほう」。
では似たケースで、AがBに対して甲宅に侵入して金品を強取するよう『教
唆』したところ、Bは甲宅に侵入して甲を殴って金品を強取したが、甲は、
殴られた際に倒れて頭を打ち、死亡してしまったらどうなるか。 Aには「強盗
致死罪」の『教唆』の罪責まで負うのかどうかが、問題となります。
判例は、Aには、「住居侵入、強盗致死罪」の『教唆犯』が成立する、と判
示しました。(大判大13.4.29)。
●教唆したのは「強盗」、実際に起きたのは「強盗致死」。
犯罪行為をなした際、予想していた以上の悪く重い結果を引き起こしてしま
った場合に、その悪く重い結果についても罪に問い、より重く科刑される犯罪
のことを、『結果的加重犯』と呼びます。
仮に、上記の例で、被教唆者が『殺意』をもって「強盗殺人」を犯したとし
ても、教唆者には『殺意』がないので、教唆者には「強盗致死罪の教唆犯」が
成立します。
最後に、教唆者に脅されて犯行に及んだ場合、罪には問われないのでしょう
か? 構成要件に該当しても、違法あるいは有責でなければ、犯罪にはなりま
せん。
考えられるのは「正当防衛」か「緊急避難」でしょうか。 正当防衛は、
相手が「不正」の場合に限られるので、このケースには該当しません。
「緊急避難(刑法37条)」というのは、違法性のない者への「反撃」又は「転嫁行為」です。
成立するための要件は、
① 現在の危難 (法益侵害の危険が切迫していること)
② 避難の意思
③ 補充性 (避難行為が成立するためには、避難行為が危難を避ける唯一
の方法であり、それ以外に危難を避ける手段がなかったこと。)
④ 法益権衡 (避難行為から生じた害が、避けようとした害の程度を超えな
かったこと。)
緊急避難が成立すると、違法性は阻却され、犯罪は成立しません。
ただ、教唆者に脅されて犯行に及んだ場合でも、③と④の要件に該当しない
可能性が高く、違法性は阻却されず、犯罪は成立すると思われます。
警察でも周知しているように、早めの相談が肝要でしょう。
今回は、以上です。
今回のお題「代表取締役等の住所非表示措置」 2024.12.1
10月1日から、商業登記規則(31条の2)が改正され、株式会社の代表取締
役等、「住所が登記」となる自然人が、DVやストーカー等の被害、過度な
営業行為等に逢っているような場合に、『住所非表示措置』の申し出をすれば
登記記録上の住所を非表示にしてもらうことができるようになりました。
一定の要件の下で、株式会社の代表取締役等の住所の行政区画以外の部分に
つき、登記事項証明書等において非表示にしてもらえます。
(例) 役員に関する事項 東京都〇〇区 【以下を非表示】
代表取締役 〇〇 〇〇
その要件は、
要件1 登記の申請と同時に申し出ること (申し出が必要)
代表取締役等の住所が、登記すべき事項に含まれる登記(設立の登記、
代表取締役等の就任・重任の登記、会社の本店、住所移転の登記等)
の申請と同時にする場合に限り申し出ることができます。
なお、住所非表示措置を希望しない旨の申し出は、いつでも可能
です。
要件2 必要書類を添付すること
① 株式会社の実在性を称する書面
② 代表取締役等の住所等を称する書面
③ 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
(住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを
証する書面)
また、住所を登記する趣旨(会社の代表者を特定する、訴訟における管轄の
決定、訴訟における訴状の送達先 等)を踏まえ、必要時には住所を表示させ
ることが、可能だそうです。
・ 官公署等から請求があった場合は、住所の情報が提供されます。
・ 利害関係人は、住所の記載された書面を閲覧できます。
なお、法務省からは、以下の注意喚起がなされています。
・ 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等に
よって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機
関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって
必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じる
ことが想定されます。 代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、こ
のような影響があり得ることについて、慎重かつ十分なご検討をお願いいた
します。
とは言え、このような状況であるならば、一刻も早く「非表示」にすること
を検討されるべきではないかと、思われます。
今回は、以上です。
今回のお題「買主の損害賠償請求・解除権の行使」 2024.12.8
インターネットでの物品の購入が盛んになりつつありますが、「届いた商品
が不良品であった。」という話も時々聞かれます。
購入時の注意書きに、『取り換え、返品には、応じられません。』と書かれ
ていることが多いですが、いわゆる『不良品』でも応じてもらえないのか?
上記『特約』があっても『取り換え、返品』に応じてもらおうとしたら、
何を根拠にすればよいか?
まず、民法562条 [買主の追完請求権] で、
「売主は買主に対し、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合する物を
引き渡す義務を負う。」 と定められています。
契約内容に適合しないものであるときは、売買契約上の義務違反(=債務不
履行)となります。
そて、引き渡された目的物に契約不適合がある場合、買主は、売主に対
し、履行の『追完』を請求できます。
目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しのうちから選択して請求す
ることができるのです。
また、民法563条 [買主の代金減額請求権] により、
「引き渡された目的物に契約不適合がある場合、買主は、売主に対し、相当
期間を定めて『履行の追完の催告』をし、その期間内に『追完』がされないと
きは、『代金減額請求』をすることができます。」
さらには、民法564条 [買主の損害賠償請求・解除権の行使] で、
「目的物に契約不適合がある場合、買主は、売主に対し、債務不履行による
『損害賠償請求』又は『契約の解除』をすることができます。」
損害賠償を請求するには、「売主の帰責事由」が必要ですが、解約には、
「売主の帰責事由」は必要ありません。
なお、民法566条 [目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間制限]で、
「売買目的物の種類・品質について契約不適合があった場合、買主は、
不適合の事実を知った時から1年以内に、売主に対して通知する義務を負います。
通知義務を怠った買主は、契約不適合を理由とする権利を行使できなく
なります。 ただし、売買目的物の引渡し時に売主が契約不適合について悪意
・重過失があったとき(証明はなかなか難しいですが)は、1年以内に通知を
しなくても契約不適合を理由とする権利を行使できます。」
(注 : 民法166条 [債権等の消滅時効] により、
『債権(数量の不適合も含む)は、債権者(買主)が「権利を行使できることを
知った時」から5年間、「権利を行使できるとき」から10年間行使しない
ときは、『時効』によって消滅します。』)
今回は、以上です。
今回のお題「相続人は誰か ? 」 2024.12.15
テレビのドラマで、金に困った息子が、資産家の父親を殺害して遺産を手に
入れようと、完全犯罪を計画するも、優秀な刑事(若しくは探偵)の活躍で失敗
し、殺人犯になるというストーリーを時々目にします。
問題1 この父親を殺した息子は、相続人となれるのか?
答え なれません。
亡くなった父親(被相続人)を殺した息子は、『欠格事由』に該当し、相続人
になることは出来ません。 (民法891条1項)
問題2 亡くなった父親(被相続人)には、配偶者(妻)がいて、殺人を犯したの
は、ひとり息子。 その息子には奥さん[嫁]と、ひとり娘[孫]がいたとして
亡くなった父親の相続人は、誰になるのか?
答え 奥さん(2分の1)と、孫娘(2分の1)
・ 嫁は、直系卑属ではないので、相続人ではありません。
・ 「相続放棄」のケースとは異なり、相続欠格者の子供は、相続人
となります(『代襲相続』)。
(民法887条2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は
第891条の規定に該当し、若しくは廃除[注]によって、その相続権を
失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。)
問題3 その後、相続人となった妻が死んだ場合、誰が相続人となるか?
答え 孫娘(のみ)
・ 母親は殺していないのに、なぜ息子は相続人になれないのか?
民法891条によります。 『次に掲げるものは、相続人になる
ことはできない。 1項 故意に被相続人又は相続について先順位
又は同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたた
めに、刑に処せられたもの。)
殺された父親は、犯人の息子からすると、母親の相続に関して
同順位(第一順位)に当たります。
問題4 さらにその後、相続人となった孫娘が死んだ場合、誰が相続人と
なるのか?
(被相続人である孫娘に、配偶者と子供がいないケース。)
答え 犯人である息子(2分の1)、嫁(2分の1)
・ 息子が殺したのは父親であり、娘の相続に関しては(同順位の
者でもないので)、『欠格事由』には該当しません。
・ 娘からみて、母親は直系尊属になるので、相続人となります。
サスペンスドラマも、登場人物の親族関係をよく把握することで、展開の
楽しみ方に、深みが増しそうです。
今回は、以上です。
[注] 『廃除』というのは、虐待などがあって、相続をさせたくない者が、
家庭裁判所に請求して「推定相続人」から相続人の資格を奪ってもらう
制度です。
今回のお題「利益相反行為(親子間)」 2024.12.22
例えば、親名義の不動産を、未成年の自分の子供に買わせる契約は、問題
ではないか。というのが問題の本質です。 親の言いなりになりかねません。
『利益相反』というのは、文字通り「お互いの利益が、相反すること」。
一方が特になれば、一方が損をする状況です。
民法826条1項は、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為
については、親権を行うものは、その子のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。」 と定めています。
親がプラス、子供がマイナスになる可能性がある場合は、家庭裁判所が選任
した特別代理人が子供を代理して、親と交渉します。
ただ、「親がプラス、子供がマイナスになる可能性があるケース」には、
判断が微妙なものも多数考えられます。
(司法書士試験でも、よく問題になります。)
ケース1 「親が自己の債務を担保するために、未成年の子供の所有不動産に
抵当権を設定する行為」
⇒ 利益相反に当たります。
ケース2 「親が自己の用途に使う目的で、未成年の子供の名において金銭
消費貸借契約を締結するために、子供の不動産に抵当権を設定する行為」
⇒ 利益相反行為に当たりません。(子供がお金を借りて、自分の不動産に
抵当権を設定するにすぎません。)
ケース3 「親が子供の学費に使う目的で、自己の名において金銭消費貸借
契約を締結するために、未成年の子供の不動産に抵当権を設定する行為」
⇒ 利益相反行為に当たります。
ケース4 「親と子供との間における、子供に有利になる遺産分割」
⇒ 利益相反行為に当たります。(親子で遺産分割協議を行うこと自体が、
親が得をして、子供が損をする可能性があるので、利益相反行為に
なります。)
微妙なケースも多いですが、判例は『利益相反行為であるかどうかは、
行為の外形から客観的に判断すべきであって、親権者の意図や動機から
判断すべきではない。』(最判昭53.2.24) [外形標準説]
⇒ 「行為の動機」「目的」「結果」を判断材料にいれてはいけません、
ということです。
なお、親権者が「利益相反行為」を行った場合には、『無権代理行為』と
なり(最判昭46.4.20)、効果は「本人(子供)」に帰属しません。
そして、子が成年になった後には「追認」することができ、追認があると
当該行為の時に遡って効力を生じます。
とはいえ、親子間で売買等「利益相反」に該当する行為をする予定となった
ときは、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てることが必要です。
今回は、以上です。
今回のお題「利益相反行為(企業内)」 2024.12.29
例えば、会社の取締役がその地位を利用して、会社の利益を犠牲にして、
自己又は第三者の利益を図るおそれがあるケースについては、会社ひいては
株主の利益を保護するため、事前に取締役会(取締役会非設置会社では株主
総会)の承認を受けなければならないとしています。 (会社法356条)
具体的には、
① 取締役が自己若しくは第三者のために、株式会社と取引をしようとする
場合。 (利益相反取引「直接取引」)
② 株式会社が、取締役の債務を保証すること、その他取締役以外の者との
間において、株式会社と取締役との利益が相反する取引をしようとする
場合。 (利益相反取引「間接取引」)
もし、会社の承認を得ずに「利益相反取引」をした場合、会社と取締役との
間の取引は無効となります。
ただし、会社は第三者の悪意(当該取引が利益相反取引に該当し、かつ、
取締役が会社の承認を得ていないことを知っていること)を証明しない限り、
第三者には取引が無効であることを主張できません。
(最判昭43.12.25、最判昭46.10.13)
そして、利益相反取引によって会社に損害を生じた場合には、利益相反取引
をした取締役は、その任務を怠ったものと推定され、これによって生じた損害
を賠償する責任を負います。 (会社法423条)
なおかつ、自己のために利益相反取引をした取締役の責任は、任務を怠った
ことが取締役の責めに帰すことができない事由によるものであることをもって
免れることができません(無過失責任)。 (会社法428条)
また、利益相反取引で任務を怠ったと推定される取締役は、取引した張本人
だけではありません。 ⅰ 取引した取締役 はもちろんのこと、
ⅱ 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役
ⅲ 当該取引に関する取締役会の承認決議に賛成した取締役
も、任務懈怠責任を問われます。 (ⅱ、ⅲの取締役は「過失責任」です。)
上記責任は、総株主の同意があれば免除することができます。(会社法424条)
自己のためにした利益相反取引でも、免除できます。 (会社法428条2項)
逆に言えば、総株主の同意がなければ、免除されません。
今年は、以上です。
今回のお題「使用者責任」 2025.1.12
運送事業者の従業員による業務上の交通事故や、金融機関職員の横領等、
被雇用者が加害者となる事件が、後を絶ちません。
会社幹部の謝罪会見の報道はよく目にしますが、会社に損害賠償責任は、
あるのでしょうか?
答えは、民法715条にあります。
1項 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につい
て第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意
をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、
この限りではない。
2項 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3項 前二項の規定(1項2項)は、使用者又は監督者から被用者に対する
求償権の行使を妨げない。
平たく言うと、『使用者は、被用者が不法行為により第三者に損害を加えた
場合、被用者の行為が使用者の事業の執行についてなされたものであるときは
第三者に対して損害賠償責任を負うよ。
でも使用者に被用者の選任監督上の過失がない時は免責されるよ。』です。
では、なぜ使用者は責任を負わなければならないのか。見解は大きく二つ。
① 使用者は他人を使用して活動範囲を広げて利益を得ている以上、それによ
って生じた損害を負担すべきとの『報償責任の原理』に求める説。
② 被用者による加害行為が客観的に使用者の領域の危険に由来するものとい
えれば使用者はその責任を負うべきであるとする『危険責任の原理』に求め
る説。
①、②の説は相互に矛盾するものではないので、両者に根拠を求める説もあり
ます。
判例も、『利益の存するところに損失をも帰せしめる(最判昭63.7.1)』と
判示しています。
1項但書については、「免責立証が認められた事例は皆無であり、同但書は
空文化している。」との指摘があるようです。
なお「失火責任」に関しては、『被用者に失火につき重過失』があるときは
その選任・監督につき使用者に重過失がなくても、使用者は責任を負う。との
判例があります。(最判昭42.6.30)
また3項で、使用者は被用者に対して求償できると書かれてていますが、
「支払った全額を求償できる訳ではなく、損害の公平な分担という見地から、
『信義則上相当と認められる限度』においてのみ認められる。」との判例が
あります(最判昭51.7.8)。
更には、最近の判例(最判令2.2.28)では、『損害賠償をした被用者の使用
者に対する求償(逆求償)』も認められました。使用者責任の趣旨を「報償
責任の原理」と「危険責任の原理」に求めているようです。
今回は、以上です。
今回のお題「権利義務取締役」 2025.1.19
横綱 照ノ富士 の引退が発表され、大相撲は「横綱不在」となりました。
これが会社であれば、どうでしょうか。 代表取締役が、不祥事等で辞任
しても、他の取締役が代表取締役に就任すれば、この辞任は認められます。
では1人しかいない取締役は、「辞任」できるでしょうか。 この「辞任」
を認めると、会社の運営ができなくなります。
このような状況を避けるために、会社法346条1項は、次のように定めて
います。
『役員(取締役・監査役・会計参与)が「任期満了」又は「辞任」により退任
したことで役員が欠けた場合、又は会社法若しくは定款で定めた員数が欠け
た場合には、当該役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員と
して権利義務を有する。』 (権利義務承継役員)
会社法で定めた員数の例としては、「 取締役会設置会社 においては、取締
役は、3名以上でなければならない。(会社法331条5項)」に基づいて、
3人の取締役のうちの1人が「辞任」しても、取締役としての権利も義務も
なくなりません。
従って、取締役会で議決権を行使する等、業務執行権を行使できる一方で、
役員等の会社や第三者への損害賠償責任も負わなければなりません。
「自分はもう取締役ではないから。」とは主張できないのです。
そもそも「退任登記」が認められません。
権利義務取締役(役員)が退任するためには、会社の責任として後任の取締役
を選任すればよく、権利義務取締役は、取締役会に働きかけて、役員選任の
株主総会を開催してもらえばよいわけです。
最後に、司法書士試験の過去問です。 (平成22-34-ウ)
問 株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者については、その
者が職務の執行に関し不正の行為をした場合であっても、解任の訴えを提起
することはできない。
答 ◯ 346条1項に基づき退任後も権利義務を有する役員につき、職務執
行に不正な行為又は法令・定款に違反する事実があったとしても、854条
の「解任の訴え」を適用ないし類推適用することはできない。
(最判平20.2.26) ⇒ 後任の取締役を選任すればよい。
もう1問 (平成26-30-オ)
問 3人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締役会設置会社において
取締役として代表取締役A並びに取締役B、C及びDの4人が在任している
場合において、Aが取締役を辞任したときは、Aは、新たに選定された代表
取締役が就任するまで、なお代表取締役として権利義務を有する。
答 × 346条1項があっても、取締役Aの辞任によっては、定款で定めた
取締役の最低人数3名に欠けることとはならないため、Aは取締役としては
権利義務を有するこなく、退任することとなる。
代表取締役であるAの辞任によって、代表取締役の最低員数1名に欠ける
こととなるが、Aは前提資格である取締役としての権利義務を有することな
く退任する以上、代表取締役としての権利義務のみを有することはなく、
代表取締役も退任することとなる。
⇒ 代表取締役は、取締役でなければならない。
取締役会で、B、C、Dの中から、新しい代表取締役を選任する。
今回は、以上です。
今回のお題「支払督促制度」 2025.1.26
先週の新聞記事で『支払督促制度を利用して、詐欺事件の被害金を取り戻す
ために凍結された銀行口座に強制執行をかけるという事件が発生した。』との
記事が出ていました。
制度的には、被害者以外でも、強制執行を行えば、凍結口座からお金を引き
出せるようです。
では、なぜ新聞で取り上げられ、最高裁判所も全国の地裁、簡裁に同様の事
例がないかの調査を指示したのでしょうか。
「強制執行」というのは、裁判所が資金を貸した側の申し立てによって、
借りた側の財産を強制的に差し押さえて、回収する手続きです。
そして、この強制執行を行うためには、『債務名義』というお墨付き(根拠
書面)が必要になります。 『債務名義』になるのは、①賠償を命ずる判決、
②公証人が作成する公正証書、③簡裁が出す支払督促、等です。
①の「判決」は、裁判に基づいて作成されます。 ②の「公正証書」は、
国の認めた公証人という資格者が、二人の立会人に立ち会わせたうえで作成
された、「支払に応じる」の記載された信憑性の高い書面です。
では、③の「支払督促」はどのように発行されるのでしょうか。
まず、発行するのは、簡易裁判所ではなく、簡易裁判所の書記官です。
そして、支払督促は、債務者を審尋(質問等での確認)をしないで発付され、
債務者に送達されます。(「公示送達(裁判所の掲示板に掲示して、2週間経っ
たら送達されたとみなす制度)」は使えません。必ず送達が必要です。)
つまり、書記官は債務者と接触することなく、債権者の書類のみに基づいて
手続きを進めます。
支払督促が発付された後、債務者から異議(督促異議⇒支払督促は効力を失
い、通常訴訟に移行する)がなければ、債権者の申してにより『仮執行宣言』
がなされます。
仮執行宣言付きの支払督促(2回目)は、債権者と債務者に送達されます(2
回目の支払督促は、公示送達も可能です。)
そして、この仮執行宣言付きの支払督促に対して債務者から異議(督促意義
⇒支払督促は失効せず、通常訴訟に移行する)がない、又は異議が裁判所で却
下されたときは、支払督促は『確定判決』と同一の効力を有し、債務者の財産
への差押えが可能になり、今回の事態にいたっています。
なお、今回の差押事件については、詐欺事件の被害者側が、「その目的物
(凍結預金)が債務者の責任財産ではないとして、強制執行の排除を求める訴え
(第三者異議の訴え)を起こしているようです。
最後に、今回の一連の報道を読んでの素朴な疑問なのですが、債権者は債務
者が詐欺事件で凍結されている預金資産を持っていること、および、その特定
の口座をどのように把握したのでしょうか・・・。 裁判所は、その存在を教
えてはくれません。
今回は、以上です。
今回のお題「役員の損害賠償責任」 2025.2.2
先日来「某放送局」が世間を賑わせています。 CМの差し止め等で、
何百億円からの損害が出るかもしれないとも、報じられています。
会社法423条は『役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査
人)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害
を賠償する責任を負う。』 と定めています。
役員等は「任務を怠って」「損害が発生する」、プラス「故意または過失」
があると、損害賠償責任が発生します。
そして、この損害賠償責任は『総株主の同意』がなければ、免除することが
できません。(会社法424条)
ある程度の規模の会社になると、株主全員が同意することは、あまり期待
できないでしょう。
そこで、この責任を回避するために経営判断が委縮することがないように、
責任を「一定額まで」軽減できる、いくつかの制度が用意されています。
(1) 株主総会決議による責任の一部免除(会社法425条)
役員等が職務を行うにつき『善意でかつ重大な過失ない」ときは、賠償責任
を負う額から「最低責任限度額」を控除して得た額を限度として、株主総会の
特別決議(株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成が必要 )によって、一部免除ができます。
(注)『善意』というのは、そのような事実があったことを「知らなかった」
ことです。 知った後は『悪意』となります。
参考 「最低責任限度額」= 控除できない額 (ざっくりと年間報酬の)
・代表取締役、代表執行役 6年分
・業務執行取締役、同執行役 4年分
・非業務執行取締役、その他の役員等 2年分
(2) 取締役会決議による責任の一部免除(会社法426条)
一部免除できるのは、①取締役が2人以上いる監査役設置会社で、
②登記された「定款」の定めがあり、 ③役員等が「善意無重過失」で、
④株主に対し「公告」又は「通知」をし、 ⑤総株主の議決権の100分の
3以上の議決権を有する株主が異議を述べなかった場合 に限られます。
(3) 責任限定契約(会社法426条)
一部免除できるのは、①非業務執行取締役等が「善意無重過失」で、
②「あらかじめ株式会社が定めた額」と、「最低責任限度額」とのいずれか
高い額を限度とする旨の『契約』を、非業務執行取締役等と締結できる旨の
登記された「定款」の定めがあることです。
なお、役員等がその職務を行うにつき「悪意又は重大な過失」があったとき
は、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負いま
す。(会社法429条) この「第三者」には、株主も該当します。
役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合におい
て、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯
債務者となります。(会社法430条)
今回は、以上です。
今回のお題「詐欺罪・窃盗罪」 2025.2.9
先日、警察庁から「2024年犯罪統計」が公表されました。統計によれば、
刑法犯は3年連続で増加しているそうです。
中でも『詐欺』は件数で24.6%増の、5万7,324件、被害額は89.1%増
の3,075億円。
このうち、オレオレ詐欺などの『特殊詐欺』が、721.5億円。 投資詐欺、
ロマンス詐欺などの『SNS型詐欺』が、1268億円にも上るそうです。
「詐欺」が法律上どのように定められているかというと、条文はシンプルです。
まずは『刑法』246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた
者も、同項と同様とする。
(注) 以前は「懲役」「禁固」と区別されていましたが、令和4年の法改正で、
今年の6月から「拘禁刑」一本となります。
「懲役」に科されていた『刑務義務』が、義務でなくなります。
窃盗罪(刑法235条)は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
司法書士試験で取り上げられるポイントをいくつかご紹介します。
・ 詐欺罪の欺く行為は、処分行為に向けられたものである必要があります。
噓を言って注意をそらす行為は、欺く行為とはいえず、詐欺罪は成立せず、
窃盗罪が成立します。
・ 欺く行為は、人に向けられたものである必要があります。機械(例ATМ)
に対する詐欺罪は成立せず、窃盗罪が成立します。
・ 詐欺罪が成立するためには、相手方が欺く行為により錯誤に陥り、処分行
為をすることが必要です。
⇒ チケットを買わず、多数の観客にまぎれてコンサート会場に入場する
行為は、処分行為がなく、詐欺罪とはなりません。
(「利益窃盗」を罰する規定がないので、不可罰となります。)
・ 代金を支払う意思がないのに、レストランで食事を注文する行為には、
詐欺罪が成立します。
注文の段階では支払う意思があったが、その後支払う意思がなくなり、
支払ったと嘘を言って逃走する行為は「詐欺利得罪(2項)」となります。
なお、嘘を言わず、隙を見て逃走した場合には、不可罰となります。
詐欺の被害に遭った場合の対応については、民法96条に規定があります。
詐欺又は脅迫による意思表示は、取り消すことができる。
2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において
は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その
意思表示を取り消すことができる。
3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失
がない第三者に対抗することができない。
やはり、司法書士試験に取り上げられるポイントです。
・ (3項の)善意無過失の第三者がいる場合でも、当事者間では取り消すこと
はできます。 ただし、取消後の第三者との関係は「対抗関係」となり、
表意者と第三者のうち、先に対抗要件(例えば登記)を備えた方が勝ちとなり
ます。
・ 欺罔者(騙した人物)に「錯誤に陥れる故意」と「それに基づいて意思表示
をさせる意思」の『二重の故意』がなければ、詐欺とはならないとの判例が
あります。(大判大6.9.6)
⇒ 司法書士試験では、次のように出題されました。 平成13-1-イ
問 Bは、C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽
の説明を受け、これを信じてAに同様の説明をし、Aもこれを信じてBから
甲薬品を購入した場合、Aは、Bとの間の売買契約を詐欺を理由に取り消す
ことができる。
答 × Bは、C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの
虚偽の説明を受け、これを信じてAに説明しているため、『Aを欺いて錯誤
に陥れる意思を有していない』。したがって、BはAに対し詐欺を行ったと
はいえず、Aは、Bとの間の売買契約について詐欺を理由に取り消すことは
できません。
最後にもう1問。 平成20-25-オ
問 不実な請求によるいわゆる「訴訟詐欺」を目的として、裁判所に対し訴え
を提起したとき、すなわち、訴状を裁判所に提出したときには、詐欺罪の
実行の着手が認められる。
答 〇 訴訟詐欺の場合、不実の請求を目的として訴状を裁判所に提出した
時点で、詐欺罪の実行の着手を判例は認めています。 (大判大3.3.24)
被害の数字を見れば、どんなに注意をしても、し足りることはなさそうです。
「自分だけは大丈夫。」と油断することなく、心して暮らしていきましょう。
今回は、以上です。
今回のお題「取締役の欠格事由」 2025.2.23
会社員としての出世は別問題として、会社法には「取締役になれない人」が
法定されています。これを『欠格事由』といいます。
欠格事由に該当する人を取締役に選んでも、「決議内容が法令に違反する」
ので、その決議は当然に無効になります。
会社法331条 (取締役の資格等)
次に掲げる者は、取締役となることができません。
① 法人
② 削除
③ 会社法関連の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行
を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(執行猶予中の者を含む。)
④ 会社法関連以外の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を
終わるまで、又はその執行を受けることが亡くなるまでの者
(執行猶予中の者を除く。)
何点か補足します。
①に関して、「株式会社」では欠格事由ですが、「持分会社(合名、合資、
合同)」では、法人は『社員』となれます。
[注] 持分会社の社員というのは、従業員のことではなく、『業務執行の
権限』を持つ立場の人のことです。 (「定款」で別段の定めが可能。)
②「削除」に関し、令和元年の改正までは、『成年被後見人』『被保佐人』
であることは欠格事由でしたが、削除されました。
ただし、「成年後見人」承認、「保佐人」の同意が必要です。
③④に関しては、以下のように「会社法関連」の方が、厳しくなっています。
会社法関連 会社法関連以外
刑の種類の制限 なし あり(禁固以上)
執行猶予中の者 含む 含まない
復権時期 2年経過後 終了 又は 失効 時
なお、「未成年者(法定代理人の同意が必要)」「破産者」は欠格事由では
ありません。
ただし「破産者」については、民法の『委任の終了』の規定に基づき、
破産開始決定を受けたときは、「取締役を退任」することになります。
それでも、「破産者」は欠格事由ではないので、再度、取締役に選任する
ことは可能です。
司法書士試験では、次のような形で出題されます。 平成22-29-オ
問 会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任しよう
とする日の3年前にその刑をの執行を終えた場合であっても、取締役になる
ことができない。
答 × 会社法関係の法律違反の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わっ
た日から2年を経過しない者は、取締役になることができません。
本問では、会社法上の特別背任罪を犯し、懲役に処せられていますが、
取締役に就任しようとする日の3年前にその刑の執行を終えているため、
取締役となることができます。
以上の内容は、家族のみの経営でも、株式会社であれば該当しますので、
ご注意ください。
今回は、以上です。
今回のお題「党員の除名処分」 2025.3.2
兵庫知事選をめぐり、某政党の県会議員が党から除名処分を受けました。
この党の処分に対し、処分を受けた議員さんは、裁判所に救済を求めることは
できるでしょうか。
少し状況は違いますが、昭和の終わりに政党と除名された議員との間で争わ
れた裁判の結果についてご紹介します。 最高裁まで行った事案です。
事案 Aは、X党の幹部であり、X党が所有し、党役員等に利用させてきた家
屋に居住していた。AがX党により除名処分を受けたため、X党は、Aに
対し上記家屋の明け渡しを求める訴えを提起した。
最高裁は、「政党の内部的自立権に属する行為は、法律に特別の定めのない
限り尊重するべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対して
した除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるの
が相当である。」として政党の自立権に配慮した上で、「政党が党員に対して
した処分が一般市民法秩序と直接関係を有しない内部的な問題にとどまる限
り、裁判所の審査権は及ばない。」としました。
その上で、「右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても
右処分の当否は、政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の
事情のない限り、右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適
正な手続きに則ってされたか否かによって決すべきであり、審理もその点に限
られる。」としました。 (最判昭63.12.20)
なお、この判例は、政党の重要性に鑑みて政党の自律性に配慮したものと考
えられます。 政党の重要性については、「法人に政治献金をする自由がある
か」が問題とされた八幡製鉄事件で最高裁が、「憲法は、政党の存在を当然に
予定しているというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素
であり、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である。」と判示していま
す。 (最大判昭45.6.24)
この事件に関する問題が、司法書士試験 平26-3-エ で出題されました。
問 政党は、議会制民主主義を支える上において重要な存在であるから、その
組織内の自律的な運営として党員に対してした処分は、それが一般市民法
秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまるものであっても、司法
審査の対象になる。
答 × (上記判例参照)
このような考え方は、『部分社会の法理』と呼ばれます。
他には「国立大学における単位認定行為」や「県議会議長の県議会議員に対す
る発言の取消命令の適否」などが挙げられますが、過去には部分社会の法理と
して司法審査の対象にはならないとされていた『地方議会議員に対する「出席
停止」処分』が、令和2年に判例変更され、審査の対象になるとされました。
時代の移り変わりや、状況の変化により、過去の判例がそのまま踏襲される
とは限らない世の中になっているのかもしれません。
今回は、以上です。
今回のお題「指名委員会等設置会社」 2025.3.9
経営問題に揺れる、大手N自動車ですが、新聞記事に「現社長退任で調整。
後任社長候補の選定を取締役会に提案する『指名委員会』が議論に入った。」
と出ていました。
『指名委員会』? あまり聞き慣れないですよね。
普通の株式会社では、取締役が代表取締役を監査するという仕組みになって
いますが、代表取締役が「人事権」と「報酬決定権」を握っているのですから
なかなか機能しにくいというのが現実のようです。
そこで「委員会」という制度が作られました。『指名委員会等設置会社』に
は、3っの「委員会」があって、それぞれに別の役割があります。
『指名委員会』 株主総会に出す、「人事案」を決めるところです。
株主総会に提出する取締役及び会計参与の選任・解任に関する議案の内容
の決定 (会社法404条1項)
『報酬委員会』 個々の役員の報酬を決めるところです。
執行役・取締役・会計参与の個人別の報酬等の内容の決定
『監査委員会』 監査と会計監査人の選解任議案を作るところです。
①執行役、取締役の職務執行の監査、監査報告の作成
②株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の
内容の決定 (執行役が、支配人その他の使用人を兼ねるときは、
当該支配人その他の使用人の報酬の内容についても決定。)
この3つの「委員会」は、必ず必要になります。そして各委員会のメンバー
は各3人以上で、かつ、その過半数は社外取締役(社外の人間)でなければ
なりません。 このメンバーは、取締役会により、取締役の中から選ばれ、
各委員の兼任も認められています。
また「指名委員会等設置会社」では、取締役は「経営方針」は決めますが、
業務の執行は、『執行役』が行います。 執行役やトップである代表執行役
(指名委員会等設置会社には、「代表取締役」というポストはありません。)
は、取締役会が選びます。 取締役の中から選ぶこともできますし、外部から
選ぶこともできます。(監査委員は、自己監査になってしまうので、執行役に
はなれません。) そして取締役会は、この執行役に大幅に権限移譲ができる
仕組みになっています。
ただ、この制度の趣旨から、以下の重要事項は執行役に委任できません。
① 委員の選定及び解職
② 執行役の選任及び解任
③ 代表執行役の選定及び解職
結局、人事権は持てない仕組みになっています。
また、取締役、執行役、代表執行役の任期は1年です(普通の株式会社では
任期は、2年)。 人事権がないうえに、任期も短い。 報酬は、報酬委員会
が決める。 つまり、外部の者から評価を受けないと、取締役等には選ばれな
いし、給料も上がらないのです。
そんなわけで、導入後「全く流行らなかった制度」と聞いていたので、今回
N自動車がこの制度を採用していたので、ちょっとビックリしました(勉強不
足)。
最後に、司法書士試験の過去問です。 平成23-31-エ
問 指名委員会等設置会社において、執行役が2人以上ある場合の代表執行役
の選定は、執行役の過半数をもって行う。
答 × 取締役会が、執行役の中から代表執行役を選定します。
今回は、以上です。
今回のお題「合同会社」 2025.3.16
世の中には、株式会社のほかに「持分会社」という形態があります。
「持分」というのは、会社に対する経営権のことで、原則として所有と経営が
分離していません。したがって、
「持分」には、持分会社の業務執行権と代表権が含まれています。
持分会社には、①合名会社、②合資会社、③合同会社という3つの種類が
ありますが、「無限責任社員」といって、会社の負債を無制限に責任を持つ
社員が含まれる①合名会社と②合資会社は、ほとんど見かけません。
一方、合同会社は「有限責任社員」のみで、自分の出資財産にしか責任を
負わず、しかも株式会社に比べて手続きが簡易な部分が多いので、最近多く
見かけるようになりました。
今回は、株式会社との比較で「合同会社」とはこんな会社というのを取り
上げたいと思います。
(1) ・出資をする人を「社員」といいます。 (「株主」とは言いません。)
・その社員が会社を経営します。
・原則は共同経営ですが、定款で「業務を執行する社員」を決めること
はできます。
・「定款」又は「定款の定めに基づく社員の互選」によって、業務を執行
する社員の中から合同会社を代表する社員を定めることもできます。
(2) ・株主がいないので、株主総会はありません。
・会社の意思決定は、多数決(社員の過半数)で決めます。
・ただし、「定款変更」は、(原則)総社員の同意が必要です。
(株式会社では、議決権数=株式数の3分の2以上で可能。)
(3) ・法人も業務執行「社員」になれます。
(「業務執行者」を選任して、会社に届け出る必要があります。)
(株式会社では、法人は 業務執行者=取締役 にはなれません。)
・会社を代表する社員になることもできます。
(4) ・いろいろな手続きが簡略化されています。
・会社設立時に、定款の「公証人による認証」がいらない。
(株式会社では、必ず必要で、認証がないと設立登記ができません。)
・設立時の印紙代が安い。(資本金の1000分7であることは、株式会社
と変わりませんが、税額が少ない場合の最低金額が、株式会社が15
万円なのに対して、合同会社は6万円です。)
・決算の公告が必要ない。但し債権者には閲覧請求が認められています。
(株式会社は、どんなに小規模な会社でも、公告が必要です。)
・業務執行社員には、任期がない。(株式会社の取締役には、(原則)2年
の任期があり、その都度「重任登記」が必要です。)
(5) ・合同会社でも「現物出資」は可能ですが『評価の適正を担保する制度』
はありません。
(株式会社の場合は、一部の例外を除いて裁判所の選任した「検査役」
の検査を受けて、その報告が裁判所になされ、変更命令を受けることが
あります。)
・払込み・給付額の2分の1以上を資本金に組み込れなければならないと
いう制限はありません。(株式会社では、2分の1制限があります。)
合同会社(持分会社)には、「準備金」の概念がないので、組み入れな
かった額は、「剰余金」になります。
(6) ・「退社」するのに、業務執行社員全員の承諾がいります。
(株式会社の株主は(原則)自由に所有する株式を処分できます。)
・「業務執行社員」が退社するには、他の社員全員の承諾が必要です。
以上のように、「合同会社」は社員の信頼の上に成り立っているので、
かなり自由にいろいろな事を決められる設計になっています。
従って会社の規模は小さくならざるを得ない部分はありますが、「定款変更
(総社員の同意)」により、、株式会社に『組織変更』をすることができます。
この場合には、株式会社の「設立の登記」と、合同会社の「解散の登記」
が必要になります。
最後に司法書士試験の過去問です。 平成24-33-イ
問 合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となることができる。
答 〇 合同会社(持分会社)の社員となりうる法人の種類は限定されていない
ため、法人の目的の範囲内の行為であれば、合同会社(持分会社)であって
も、他の合同会社(持分会社)の業務執行社員となることができます。
今回は、以上です。
今回のお題「推定相続人の廃除」 2025.3.23
ドラマなどでよく、親子間で揉めて「お前には、相続させない。」と言い放
たれる場面が出てきます。
そんなことが出来るのか?
「自分の財産なのだから当然でしょう!」と思われるかもしれませんが、
『遺言』に「息子の A男 には、遺産は一切やらない。」と残しても、実は
「遺留分」と言って、法定相続分の半分は、他の相続人に請求できるという
法律があるのです。(民法1042条以下) これは「相続人の生活を保障したい。」
という相続の趣旨と、「死者の最終意思を尊重したい」という遺言の趣旨を調整する制度です。
それでも、①被相続人に対する虐待又は重大な侮辱、②推定相続人の
著しい非行 がある場合に、家庭裁判所に「廃除を請求」して、審判を受ける
ことによって、推定相続人から「相続人の資格を奪ってもらう」ことが可能に
なります。 家裁への請求は、生前でも遺言でも可能です。
また、理由を問わず、いつでも取消すこともできます。
廃除者に対して「遺贈」をすることは可能ですし、廃除された者の相続分は
代襲相続人(被相続人の孫=廃除者の子)に相続されます。
なお、兄弟姉妹には「遺留分」はなく、『遺贈』により法定相続分を渡さな
いことが可能なので、兄弟姉妹は『廃除』できません。
『廃除』と似ているが、別の制度が『相続欠格』です。(民法891条以下)
ドラマでいうと息子が遺産目当てに父親を殺してしまったようなケースです。
こちらは、法律上当然に欠格者になるので、手続きはいりません。
どんな者が「相続欠格者」になるかというと、
①故意に被相続人又は相続についての先順位若しくは同順位にある者を死亡
するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者
(例 殺人罪、殺人未遂罪、殺人予備罪)
②被相続人の殺害されたことを知って告発又は告訴しなかった者
(配偶者又は直系血族を除く)
③詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、
取消させ、又は変更させた者
④相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
なお、 相続欠格では「遺贈を受ける権利」も喪失します。 相続欠格者の
相続分は代襲相続人が相続します。
最後に、司法書士試験の過去問です。 平成27-22-ウ
問 夫A及び妻Bの子であるCが、故意にAを死亡させて刑に処せられた場合に
おいて、その後にBが死亡したときは、Cは、Aの相続について相続人になる
ことができないほか、Bの相続についても相続人になることができない。
答 〇 父に対する殺人により刑に処せられた子は、父の相続に関して相続人
になることができないほか、父の配偶者であった母の相続に関しても、相続
人になることはできません。 同順位にあるものを死亡させたといえるから
です。
今回は、以上です。
今回のお題「未成年者の犯罪」 2025.3.30
何年か前に、回転寿司屋で高校生が迷惑行為をして、親も損害賠償請求を
受けました。 親が責任を負う根拠は、民法にあります。
712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の
責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為に
ついての責任を負わない。
713条 略
714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合におい
て、その責任無能力者を監督する法定の義務を負うものは、その責任
無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、
監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなく
ても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。
712条の「責任能力」については、民法には明確な年齢基準は定められて
いませんが、判例では12歳前後がその基準とされています。
そして、未成年者には損害賠償を負担する経済力がないので、被害者救済の
趣旨から、責任無能力者を監督する義務を負うものに、その損害賠償をする
義務を負わせました。
司法書士試験の過去問です。 令和1年-19-エ
問 責任を弁識する知能を備えていない未成年者が、通常は人身に危険が及ぶ
ものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合には
その親権者は、当該行為について具体的に予見することができなかったとき
であっても、当該行為から生じた損害について、民法714条1項に基づく
責任を負う。
答 × 判例は、「責任を弁識する能力のない未成年者が、通常は人身に危険
が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた
場合には、その親権者は、当該行為について具体的に予見可能であるなど
特別の事情が認められない限り、子に対する監督義務を怠ったはいえな
い。」としました。 (最判平27.4.9)
(参考) 具体的な事件の概要は、小学校6年生のAが放課後に開放された小学
校の校庭で、フリーキックの練習のためにサッカーゴールに向かってボールを
蹴っていたところ、バイクを運転してその校庭横の道路を進行していた当時
85歳の被害者Bが道路に転がってきたボールを避けようとして転倒負傷し、
その後死亡したことにつき、Bの相続人らがAの父母に対し損害賠償を請求し
たというものです。
つい先日も、同じ判旨の損害賠償に関する地方裁判所の判決が、新聞記事に
なっていました。 15歳で見ず知らずの女性を刺殺した犯人とその母親に対
して遺族が損害賠償を請求した事件で、地裁は犯人に対しての損害賠償は認め
ましたが、母親に対する請求は「危害を加えるとの予見は困難で、管理義務
違反があったとは認められない。」という理由で棄却しました。
この犯人は、小学生の頃から問題を起こすことを繰り返し、少年院に入り、
仮退院するときに母親は身元引受を拒み、更正施設に入ったものの、1日で
抜け出して、その翌日に事件を起こました。 原告の「管理義務違反」の主張
に対し、母親側は「長期間施設に入っており、指導監督は施設が行っていたの
で予見は出来ず、監督義務違反もなかった。」と主張し、この主張が認められた
かたちです。
また、生成AIを悪用して作ったプログラムで「通信回線を大量に不正契
約」して売却した罪で、中高生が逮捕され東京地検に書類送検されたとの事件
事がありました。
仮に、民事の損害賠償事件も提訴された場合、「親も管理義務違反に問われ
るのか。」「親への請求は認められるのか。」も、気になるところです。
今回は、以上です。
今回のお題「株主は何ができる?」 2025.4.6
新年度が始まりましたが、3月末が決算で、6月下旬に株主総会という
会社が多い気がします。(定款の決めで何月末を決算にしてもかまわない
ですし、何か月以内に株主総会を開かなければならない、という決まりも
ないようです。)
某放送局をはじめ、諸々の事情で株主総会が揉めそうな会社も多々ありそう
な気配ですが、株主が会社の経営に関与できる場面は、「配当を受取る」以外
にも、いろいろとあります。 大株主以外でも、です。
〇 計算書類等の閲覧請求権 (会社法442条)
株主総会の案内には「計算書類等」が同封(もしくは、WEB閲覧用の
アドレスが記載)されていますが、普段から、会社の営業時間中は、いつでも
閲覧を請求することができます。 手数料を払えば謄本等の書面の交付も
請求できます。
さらに、議決権数又は発行済株式数の100分の3以上の株式保有者
(少数株主権)は、会計帳簿の閲覧・謄写請求も可能です。
〇 株主総会に関して
① 議題提案権(会社法303)
議題とは、「テーマ」です。 例:取締役を選ぶ
一定の事項を総会の目的として請求する権利です。
② 議案提案権(会社法304条)
議案とは、「具体案」です。 例:取締役を具体的に誰にするか
総会の目的事項につき議案を提出する権利です。
③ 議案要領通知請求権(会社法305条)
総会の目的事項について、自己の「議案の要領」を株主に通知すること
を請求する権利です。
②は、議決権がある株主であれば、誰でも請求可能です。
①③は、取締役会を設置していない株式会社では、1株でも持っていれば
誰でも請求可能です(単独株主権)。
一方「取締役会設置会社」では、少数株主権(総株主の100分の1以上の
議決権又は300個以上の議決権を有する株主)となります。
☆ 少数株主権としては他に
・「株主総会招集請求権」(会社法297条)
[総株主の100分の3以上の議決権を有する株主]
・「役員解任請求の訴え」(会社法854条)
[総株主の議決権数又は発行済株式総数の100分の3以上を
有する株主]
・「会社解散の訴え」(会社法833条)
[ 総株主の議決権数又は発行済株式総数の10分の1以上を有する
株主]
等があります。
④ 決議の不存在・無効の確認の訴え (会社法830条)
株主総会の決議について「決議が存在しないこと」の確認を、また、
決議の内容が法令に違反するときは、「決議が無効であること」の確認を、
いつでも、誰でも(株主でなくても)、確認の利益がある限り、訴えをもって
請求することができます。
⑤ 決議の取消の訴え (会社法831条)
ⅰ 株主総会等の召集の手続き又は決議の方法が法令若しくは定款に違反
し、又は著しく不公正なとき。
ⅱ 株主総会の決議の内容が定款に違反するとき。
ⅲ 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使し
たことによって、著しく不当な決議がされたとき。
は、決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消を請求する
ことができます。(会社法442条)
〇 株式買取請求権
さまざまなケースで、決議に反対の株主が、会社に対して、自己の株式を
買取るように請求する権利が認められています。
① 定款変更の場合 (会社法116条)
例:全部の株式を譲渡制限株式にする場合
② 種類株主総会が不要な場合 (会社法116条)
株式の併合・分割・無償割当て、単元株式数の変更、募集株式・新株予約
権の発行、新株予約権無償割当てをすることで、ある種類の種類株主に
損害を及ぼす恐れがあり、かつ、種類株主総会の決議を要しない旨の定款
の定めがある場合
③ 組織再編等の場合
事業譲渡等・吸収合併等をする場合
最後に、富太郎がよく間違える司法書士試験の予想問題です。
問 種類株式発行会社がある種類の株式を分割する場合に、当該
種類株式を有する種類株主に損害を与えるおそれがあるとして、
当該種類株主総会の特別決議により承認を得たときは、当該種類の
株主で株式分割に反対の株主は、株式会社に対し、株式買取請求を
することができる。
答 × 種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに、反対株主が買取
請求権の行使が認められるのは『種類株主総会の決議を要しない旨』
の定款の定めがある場合です。
今回は、以上です。
今回のお題「だまされたふり作戦」 2025.4.13
最近もニュースになっている 特殊詐欺 ですが、闇バイトに応募して逮捕
された『受け子』はどのくらいの罪に問われるのでしょうか。
司法書士試験の刑法で、過去に出題されました。(余談ですが、五肢
択一問題の一肢で、滅茶苦茶 長文 で 引いた 覚えがあります。)
刑法 令和2年 25-ウ
問 Aは、Bに電話をかけ、Bに対し、「Bの孫がトラブルに巻き込まれて
おり、その解決のために至急100万円が必要になるので、これからB方を
訪ねる者に100万円を渡してほしい。」旨うそを言った。Bは、詐欺では
ないかと疑い、警察に通報したところ、警察官から捜査協力を依頼され、
そのままだまされたふりをして、B方を訪ねてくる者を待った。Bが警察官
からの協力依頼を引き受けた後、Aは、Cに対し、B方に行ってBから現金
を受け取ってくれば報酬を支払う旨を申し向け、Cは、詐欺の被害金を受け
取る役割を担う認識でB方に赴いたところ、周囲で警戒していた警察官に
発見された。
この場合において、Cには、詐欺未遂犯の 共同正犯 は成立しない。
答 × 『共犯者による欺罔行為がされた後、「だまされたふり作戦」(だま
されたことに気付いた、あるいはそれを疑った被害者側が、捜査機関と協力
の上、引き続き犯人側の要求どおり行動しているふりをして、受領行為等の
際に犯人を検挙しようとする捜査手法)が開始されたことを認識せずに共犯
者と共謀の上、詐欺を完遂する上で欺罔行為と一体のものとして予定されて
いた現金の受領行為に関与した者は、その加功前の欺罔行為の点も含め、
詐欺未遂罪(刑法250条、246条1項)の共同正犯としての責任を負う。』
との判例があります。 (最判平 29.12.11)
ただ(試験勉強とは関係ありませんが)、この裁判の第1審は共犯の処罰
根拠は、共犯が犯罪結果に対して因果性を持つという点に求められるべきで
あり、「共謀加担前の先行者の行為により既に生じた犯罪結果」については、
後行者の共謀やそれに基づく行為がそれに因果性を及ぼすことはありえない。
本件は、「だまされたふり作戦」により、被告人は、共謀加担後、詐欺の
結果が生じる危険性を発生させることにつき因果性を及ぼしたとは言えないの
で『詐欺の未遂にもならない』として、詐欺未遂罪の共同正犯の成立を否定
し、無罪判決を言い渡しました。
「欺く行為があるのに、因果性を欠くで未遂にもならない。」いうのは、
無理がある気がしますが、相当に凄腕の弁護士先生だったのでしょうか。
一方、最高裁は『本件が詐欺罪の既遂に至っていたとしたら、後行者は先行
者との共謀の上で、詐欺結果に因果関係を及ぼしたことを理由に、共同正犯と
して、詐欺罪の共同正犯の成立を肯定できる。 もっとも、本件は詐欺の未遂
にとどまったので、後行者は先行者と共謀の上で、本件詐欺を完遂する上で
本件欺罔行為と一体のものとして予定されていた本件受領行為[詐欺未遂行為
の一部]に関与した。』と表現して、「詐欺未遂罪」の共同正犯の成立を肯定
しました。
つまり『共同正犯』が認められるので、『受け子』も首謀者と同罪という
ことです。 (申し渡される刑の重さには、差がつくとは思いますが。)
今回は、以上です。
今回のお題「今やっているのは何国会?」 2025.4.20
いきなりの問題で恐縮です。 今やっているのは「何国会」でしょうか。
① 常会 ② 臨時会 ③ 特別会
答えは、①。 「常会」、通常国会ともいわれます。
「常会」というのは、毎年1回招集することが憲法上要求されている国会の
会期です(憲法52条)。 毎年1月中に招集するのが常例とされ、会期は
150日です。
「臨時会」というのは、必要に応じて臨時に招集される国会の会期です
(53条)。
[1] 内閣が必要とするとき
[2] いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があるとき
[3] 衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われ
たとき。 (今年は参議院選挙があるので「臨時会」も開催されます。)
「特別会」というのは、衆議院の解散があった場合に、解散の日から40日
以内に衆議院議員の総選挙を行い、選挙の日から30日以内に招集される国会
の会期です(54条)。
こちらは今年、有るかもしれないし、無いかもしれません。
国会(各議院)が活動するために必要な最小限の出席者数(定足数)は、各々の
総議員の3分の1です(56条)。
国会(各議院)が意思決定を行うのに必要な賛成表決の数は、
原則は、出席議員の過半数。
特別の定めとして、①「出席議員の3分の2以上」必要なのが、
・ 議員の資格争訟裁判において議員の議席を失わせる場合
・ 秘密会(注)の開催
・ 懲罰による議員の除名
・ 法律案の衆議院での再議決
②「総議員の3分の2以上」必要なのが、
・ 憲法改正の発議
注 両議院の会議は、「公開」が原則ですが、出席議員の3分の2以上の
議決により、公開しない「秘密会」を開くことができます。
なお、「会期」に関して、国会は会期ごとに独立して活動し、会期中に
議決されなかった案件(議院において審議の対象となるすべての事項)は、
後会には接続しません[会期不継続の原則]。
また、議会が一度否決した案件は、同一会期中には再び議されません
[一時不再議の原則]。
衆議院の解散中において、国会の開会を要する緊急の事態が生じたときに、
参議院が国会を代行する制度[参議院の緊急集会]もあります(54条)。
最後に、司法書士試験の過去問です。 平成26-2-5
問 「特別会」は、衆議院の解散に伴う衆議院議員の総選挙後に招集される
ものであり、その会期中は、参議院は閉会となる。
答 × 『衆参両議院同時活動の原則』により、衆参両議院は、1つの国会と
して同時に活動するので、同時に招集され、閉会します。
今回は、以上です。
今回のお題「社外取締役」 2025.4.27
3月で年度が終わり、多くの会社が6月頃に株主総会を開催します。
その場で「取締役」等の役員人事の承認が行われますが、昨今、某テレビ局の
不祥事がらみで『社外取締役』の存在が取りあげられています。
そこで今回は、そもそも『社外取締役』とはどのような存在なのか。
どのような「取締役」が『社外取締役』となれるのか。 についてプレゼン
させていただきます。
「監査等委員会設置会社」「指名委員会設置会社」については、従来から
『社外取締役』の設置が義務付けられていましたが、令和元年の会社法改正
(施行は3年3月)で「327条2項」が追加され、上場企業は『社外取締役』
を置かなければならなくなりました。
設置目的は「コーポレート・ガバナンス(企業統治)を実行的に機能させ、
我が国の資本市場が信頼される環境を整備するという観点から『社外監査役』
による監督が保証されていることを国内外に発信するため、上場企業等は
『社外取締役』を置かなければならない。」というものでした。
つまり、第一義的には「経営の監視機能」で、経営の透明性を高める効果を
期待した訳です。 『社外取締役』も取締役会に出席して、会社の事業戦略・
計画に対して、社内の利害関係に囚われず、客観的な視点で意見を述べること
が、本来的には求められています。
また、社内とは別の視点から「外部からの知見の提供」によって、「経営陣
のスキルの多様化」も期待されています。 今回発表のあったABC社が、
俳優として、母として、経営者として活躍している女性二人を『社外取締役』
候補であると発表したのは、こちらの目的に重きを置いたものと思われます。
一方、従来の某テレビ局は、『社外取締役』も(前)会長の息のかかった人物
で固められ、「企業内部やその利害関係者のみでの企業経営となり、経営陣に
よって社内論理優先の経営判断が行われていた。」との批判を受けているよう
です。 ただ、問題が大事になってから叩きまくるのは、何か「後出しじゃん
けん」のような気がしないでもないですが・・・。
では、『社外取締役』が『社外』と認定されるための要件は、どのような
ものでしょうか。 会社法2条15でかなり細かく定められています。
要約しますと、
① 過去要件1
株式会社又は子会社の「業務執行者」でなく、かつ、就任前10年間、株式
会社又は子会社の「業務執行者」でなかったこと。
② 過去要件2
就任前10年間、株式会社又は子会社の役員(業務執行者を除く)であった場
合(例えは、監査役)、役員の就任前10年間、株式会社又は子会社の「業務執
行者」でなかったこと。
③ 親会社 (株式の50パーセント以上を所有) 関係者
親会社の取締役、執行役、支配人等でないこと。
④ 兄弟会社 (同じ親会社の子会社どうし) 関係者
兄弟会社の「業務執行者」でないこと。
⑤ 会社関係者の近親者
株式会社の取締役、執行役、支配人等の配偶者又は二親等内の親族 (親ある
いは子) でないこと。
最後に、会社法348条の2[業務の執行の社外取締役への委託] は次のよう
な条文です(「指名委員会等設置会社」がらみの部分省略)。
「株式会社が社外取締役を置いている場合において、当該株式会社と取締役と
の利益が相反する状況であるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行
することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、
その都度、取締役会の決定によって、当該株式会社の業務を執行することを『社外取締役』に委託
することができる。
3項 前二項の規定により委託された業務の執行は、第2条第15号イ
(上記①)に規定する株式会社の業務の執行に該当しない者とする。 ただし、
『社外取締役』が業務執行取締役の指揮命令により当該委託された業務を執行
したときは、この限りではない。」
つまり『社外取締役』も、自己の判断で「経営上の意思決定」をしなければ
ならない場面もありうるということです。
この条文に関して、某予備校が「司法書士試験の公開模試」で、次のような
問題を出してきました。(「指名委員会等設置会社」がらみの部分省略)
問 取締役会設置会社の『社外取締役』が、業務執行取締役の指揮命令により
当該会社から委託された業務を執行した場合、当該取締役は『社外性』を
喪失する。
答 〇 上記3項但書どおりです。(当該社外取締役が業務執行取締役の指揮
命令により委託された業務を執行したときは、社外取締役としての地位を
失う。) なぜなら、社外取締役が業務執行取締役の指揮命令により委託さ
れた業務を執行したときは、業務執行者からの独立性が疑われ、社外取締役
の要件を定める 会社法2条15条イ の規定の趣旨に反するからです。)
『社外取締役』の地位を失うのであって、「取締役」でなくなるわけでは
ありません。
今回は、以上です。
今回のお題「国民主権」 2025.5.4
5月3日は『憲法記念日』で祝日でした。 日本が『国民主権』の国だと
いうのは、小学生でも知っていますが(たぶん)、では「主権て何んですか?」
と質問されたら、何んと答えますか。
実は平成28年の司法書士試験の憲法の問題で、丸々1問(5肢)『主権』に
ついて問われました。 (組合せ問題から、個別の判断問題に変更してます。)
問 主権の概念には、
① 国家権力そのもの(国家の統治権)
② 国家権力の属性としての最高独立性
③ 国政についての最高の決定権
という三つの異なる意味があるとされている。
太字部分の語句が ① の意味で用いられているもの(の組合せ)は、どれか。
(ア) われわれは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視し
てはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則
に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責
務であると信ずる。 [憲法前文]
答 ② 前文第3段のにおける「主権」は、国家の性格としての最高独立性、
特に対外的側面における独立性を意味します。
(イ) 日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及び四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島
ニ局限セラルベシ [ポツダム宣言第8項]
答 ③ ここでの「主権」は、国家の統治権、すなわち立法権・行政権・司法
権など複数の国家権力を総称する観念です。
(ウ) 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は
主権の存する日本国民の総意に基く。 [憲法第1条]
答 ③ 1条における「主権」は、国の最高意思決定権、すなわち国政につい
ての最高決定権を指します。 ( ⇒ 『国民主権』 )
(エ) 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
[憲法第41条]
答 ① 41条における「国権」は、国家権力そのものを表すもの、すなわち
国家の統治権という意味で使われています。
(オ) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われわれとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土
にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍
が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存すること
を宣言し、この憲法を確定する。 [憲法前文]
答 ③ 前文第1段第1文における「主権」は、国の最高意思決定権、すなわ
ち国政についての最高決定権を指します。 ( ⇒ 『国民主権』 )
「憲法」を含む、司法書士試験の午前の択一問題は、1問だいたい3分程度
で回答していきます(35問を2時間)。 家に帰って改めてじっくりと考え直
せば正解できましたが、当日の試験会場では、緊張感と限られた時間の中で、
舞い上がってしまい、しっかりと間違えた悲しい思い出のある問題です。
今回は、以上です。
今回のお題「住居侵入罪」 2025.511
先日、小学校で父母の知人が学校に押しかけ、先生等に暴力を振るうという、
信じがたい事件が発生しました。
暴力事件はもってのほかですが、そもそも関係のない人物が、無断で校内に
入っていいのか。犯罪にはならないのか。 『刑法(130条)』には多くの
「住居侵入罪」に関する最高裁の判例があるので、いくつか簡単にご紹介した
いと思います。
〇 Aが、B宅に強盗に入ろうと考えて、B宅に赴き、Bに対して、強盗の意
図を隠して、「今晩は」と挨拶したところ、BがAに対して「おはいり」と
答えたので、これに応じてB宅に入ったケース。
⇒ 居住者、看守者の承諾が有効な場合には、意思に反する立ち入りがないの
で「侵入」には当たらず、住居侵入罪は成立しないが、錯誤に基づく承諾は
無効であるから、住居侵入罪が成立します。 (最大判昭24.7.22)
〇 Aは、マンションの上階のB方の住人の足音などか大きいと不満を抱き、
それまで付き合いのなかったB方へ行くや、鍵の掛かっていなかった玄関
ドアからB方の居間に入り込み、騒音が大きいなどと文句を言った。Bは、
Aに対し、出ていくよう求めたが、AはBからの通報で警察官が駆け付ける
までB方の居間にとどまり、騒音に対する文句を言い続けたケース。
⇒ Aは、Bの意思に反してその住居に立ち入っており、Aには、住居侵入罪
が成立します。 なお、継続犯である住居侵入罪が成立する以上、Aが
Bに退去を求められ、応じなかった場合でも、不退去罪は成立しません。
(最決昭31.8.22)
〇 Aは、窃盗の目的で、夜間、Bが経営する工場の門塀で囲まれた敷地内に
入ったが、工場内に人がいる様子だったため、工場内に入るのを断念して
立ち去ったケース。
⇒ 130条の「建造物」には、建物だけではなく、その囲繞地も含みます。
Aが、窃盗の目的で、Bが経営する工場の門塀にか囲まれた敷地内に入った
段階で、人の看守する建造物に「侵入」したものといえるので、工場に入る
のを断念して立ち去ったとしても、Aには建造物侵入罪の既遂罪が成立しま
す。 (最大判昭25.9.27)
◯ Aは、現金自動預払機の利用客のキャッシュカードの暗証番号を盗撮する
目的で、現金自動預払機が設置された無人の銀行の出張所の建物内に立ち入
り、小型カメラを取り付けたケース。
⇒ Aが、現金自動預払機の利用客のキャッシュカードの暗証番号を盗撮する
目的で、現金自動預払機が設置された無人の銀行の出張所の建物内に立ち入
った場合、そのような立ち入りが同所の管理権者の意思に反することは明ら
かであるから、その立ち入りの外観が一般の現金自動預払機利用客と異なる
ものでなくても、Aには、建造物侵入罪が成立します。(最決平19.7.2)
◯ Aは、甲警察署の中庭に駐車された捜査車両の車種やナンバーを把握する
ため、甲警察署の敷地の周囲に庁舎建物及び中庭への外部から交通を制限し
みだりに立ち入りを禁止するために設けられ、外部から内部をのぞき見るこ
とができない構造となっている高さ2.4メートルのコンクリート製の塀の
上部に上がったケース。
⇒ 警察署庁舎建物及び中庭への外部からの交通を制限し、みだりに立ち入り
することを禁止するために設置された高さ約2.4mの本件塀は、建造物侵
入罪の客体に当たり、中庭に駐車された捜査車両を確認する目的で本件塀の
上部へ上がった行為は、「侵入」に当たるから、建造物侵入罪を構成しま
す。 (最決平21.7.13)
最後に、刑法130条[住居侵入等]の条文です。
『 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若し
くは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去
しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。』
なお、傷害罪(刑法204条「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑
又は50万円以下の罰金に処する。」)、放火罪、殺人罪等、他の犯罪の手段
として犯された場合、住居侵入罪とこれらの罪は、牽連犯(注)となります。
(注)「牽連犯」というのは、『犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名
に触れる場合』をいいます。数個の行為が手段・目的、又は原因・結果の関係
にあることを要件として「科刑上一罪(その最も重い刑により処断する)」として
扱われます。(刑法54条)
今回は、以上です。
今回のお題「参議院議員選挙」 2025.7.13
20日は、3年に一度の参議院選挙。任期は6年で半数改選になります。
前に書いた「衆議院の優越」制度等がある中、参議院の存在意義は何なのか。
『日本国憲法が二院制を採用した趣旨は、異なる選挙制度(*)や議員の
任期が異なる(衆議院議員は4年)こと等によって、多角的かつ長期的な視点
からの民意を反映させ、衆議院と参議院との権限の抑制と均衡(議会の専制
防止)を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとしたもの。』と
いうのが、通説のようです。
異なる選挙制度(*)
・衆議院~「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」が同じ投票日に行われる。
『解散』による選挙がある。
・参議院~「(原則)都道府県単位の選挙区制」と「非拘束名簿式比例代表制
(政党の得票数で議席数が決まる)」が同じ投票日に行われる。
『解散』制度はない。
なお、衆議院の『解散中』は、参議院も同時に閉会となるが、内閣は、国に
緊急の必要があるときは、参議院に『緊急集会』を求めることができます。
また、国政選挙のたびに「問題提起」されるのが、『議員定数不均衡(1票
の格差)問題です。
問題(1) 投票価値の平等
判例は、憲法14条1項に定める『法の下の平等』は、選挙権に関しては、
「国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等
化を志向するものであり、各選挙人の「投票価値の平等」もまた、憲法の要求
するところであり、投票価値の平等は、単に国会の裁量権の行使の際における
考慮事項の1つにとどまるものではない。」として投票価値の平等が憲法上
保障されることを認めています。 (最大判昭51.4.14)
問題(2) 違憲問題
では、どのくらいの「格差」があると『違憲』となるのか。 そもそも、
最高裁は『違憲判決』を出したことはありません。
ただ、①『定数配分又は選挙区割りが、行政区画など国会が正当に考慮できる
諸事情を総合的に考慮した上で投票価値の較差において憲法の投票価値の平等
の要求に反する状態に至っているか否か』、上記状態に至っている場合に、
②『憲法上要求される合理的期間以内における是正がなされなかったとして、
定数配分規定又は区割り規定が憲法の規定に違反するに至っているか否か』
によって、判断されます。
問題(3) 格差何倍までなら許容されるか?
衆議院議員選挙も含めて、最高裁は「何倍までなら許容されるかということ
を、積極的には明示していません。
「参議院議員選挙」においては、
平成26年大法廷判決 最大格差1対4.77倍
『違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態』 ⇒ 合憲(違憲状態)判決
ただし、4人の裁判官が「違憲である」との反対意見を述べました。
平成29年大法廷判決 最大格差1対3.08倍 (「合区制度」導入)
『違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にはない』 ⇒ 合憲
令和2年大法廷判決 最大格差1対3.00倍 ⇒ 合憲
令和5年大法廷判決 最大格差1対3.03倍 ⇒ 合憲
ちなみに、「衆議院議員選挙」においては、最近は、
平成30年大法廷判決 最大格差1対1.979倍 ⇒ 合憲
令和 5年大法廷判決 最大格差1対2.08倍 ⇒ 合憲
では、最高裁が「議員定数の配分規定を憲法14条1項に違反して無効であ
る。」と判断した場合はどうなるのでしょうか。
先の最大判昭51.4.14の最高裁の法定意見『当該選挙を無効とすることによ
って憲法が所期していない結果が生じることを回避するために、その配分規定
に基づき既に実施された選挙の効力を無効とはせず、行政事件訴訟法31条の
『事情判決の法理』により、「選挙無効の請求を棄却」した上で、判決主文で
当該選挙が違法である旨を宣言するにとどめるという手法をとるべき。』との
見解が主流です。
最後に、今回の参議院議員選挙においても、弁護士グループの先生方が、
『2025年7月参議院議員選挙『違憲無効』訴訟を、7月22日(火曜日)に
全国8高裁6支部に「一票の不平等」を全国一斉提訴』することが、報道され
ています。 選挙の結果とともに、裁判の行方も気になります。
今回は、以上です。
今回のお題「夫婦に関する法律」 2025.7.27
「夫婦別姓」が議論される中、商業登記における『旧氏の併記』等、
登記関係でもいろいろな改正が行われています。
また、令和6年に民法(家族法)の改正時期はあり、令和8年の5月までに
施行されます(時期は未定)。
今回は、夫婦に関連する法律、判例等をご紹介します。
(1) 結婚・離婚の意思
婚姻の意思に関しては、結婚と離婚とでは、最高裁の判例の扱いが異なって
います。
① 結婚 「婚姻の意思は、戸籍の届出をする意思だけでなく、新たに夫婦と
して共同生活をしようとする意思が必要である。」 (実質意思説)
⇒ 偽装結婚は無効です。
判例『724条1項にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、
当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する
意思の合致がない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に
意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達成する方便として
仮託されたものにすぎないときは、婚姻はその効果を生じない。』
(最判昭44.10.31)
⇒ 例:単に子に嫡出子としての地位を得させるため。
② 離婚 「離婚の意思が必要である。離婚の意思は、届出をする意思で
足りる。」 (形式的意思説)
⇒ 生活保護受給継続のための離婚は、有効です。
判例『夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための
方便として協議離婚の届出をした場合でも、当該届出が真に法律上の婚姻
関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、当該協議
離婚は、その効力を生じる。』 (最判昭57.3.26)
(2) 夫婦間の財産契約
民法760条(婚姻費用の分担)「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を
考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」 (法定財産制)
民法756条(夫婦財産契約の対抗要件)「夫婦が法定財産制と異なる契約を
したときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の
承継人及び第三者に対抗することができない。」
なお、夫婦の一方が相続により取得した財産は「婚姻中自己の名で
得た財産」であり、夫婦の共有に属する財産とは推定されません。
(3) 夫婦間の契約の解除
民法754条(夫婦間の契約の取消権)「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつで
も、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利
を害することはできない。」
判例は『「婚姻中」とは、形式的にも実質的にも婚姻が継続している
ことを意味し、婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には、754条
本文の規定によって、夫婦間の契約を取り消すことはできない。』として
います。 (最判昭42.2.2)
⇒ 例:A男は、B女に対し、不動産を贈与したが、その後、A男とB女の
婚姻関係が破綻するに至った場合には、A男は、当該贈与契約を取り消
すことができない。
なお、754条は、令和6年の民法改正で削除されます。
(4) 日常家事に関する債務の連帯責任
民法761条「夫婦の一方が日常家事に関して第三者と法律行為をしたとき
は、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任
を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、
この限りではない。」
判例は『夫婦の一方が本条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を
超えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎とし
て一般的に110条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越
権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常家事に
関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由があるときに限り、
同条の趣旨を類推して第三者の保護を図るべきである。』
としています。 (最判昭44.12.18)
⇒ 「Bの妻Aが、Bの実印を無断で使用して、Aを代理人とする旨の
B名義の委任状を作成した上で、Bの代理人としてB所有の土地を
Cに売却したという事件の判決です。
(個人的には、不動産の売買を「日常家事に関する法律行為に属する」
とは、なかなか信じられないような気がしますが・・・。)
今回は、以上です。
今回のお題「内縁の妻(夫)」 2025.8.10
「内縁」は、「婚姻」と何が同じで、何が違うのでしょうか?
ものの本によれば、「内縁関係」とは『婚姻届』を提出してはいないものの、
夫婦としての実質を備えている男女の関係だそうです。
では、法律上は「何が同じ」で、「何が違う」のか?
まず、「内縁」に「婚姻」の規定が準用(類推適用)されないものです。
❶ 氏の変更 (民法750条)
❷ 子の嫡出推定 (民法772条)
❸ 配偶者の相続権(民法890条)
次に、規定が準用(類推適用)されるものです。
① 同居・協力・扶助義務 (民法752条)
② 日常家事債務の連帯責任(民法761条)
③ 婚姻費用分担
⇒ 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻生活から
生ずる費用を分担する(民法760条)
④ 近親者に対する損害の賠償(民法711条) を請求できる。
これらの規定は、『内縁関係にも類推適用される。』との判例があります。
(最判昭33.4.11)
上記判例では、『当事者の一方が正当な理由なく内縁関係を破棄したときは、
他方の者は、相手方に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できる。』
ことも判示しています。
⑤ 財産分与(民法768条) 協議上の離婚(内縁関係解消)をしたもの
ただし、『内縁夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合には、
財産分与に関する規定は類推適用されない。』との判例があります。
(最判平12.3.10)
死亡による内縁解消の際に、離婚する場合の制度である「財産分与」を類推適用すると、
『法が本来予定している(相続)制度」から逸脱するからなのだそうです。
財産分与に関する「一方の死亡」のケースは、「内縁関係の妻(夫)」にとっては、
厳しい結論になりますが、同じ死亡のケースでも、不動産の賃貸借に関しては、
様相が変わります。
ケース1 「A及びBは内縁関係にあり、甲建物に共に住んでいたが、
Aは亡くなった。A及びBが住んでいた甲建物が、Aが賃借していた家であり、
Aに相続人がいない場合は、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった
同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する(借地借家法36条)
ので、BはAの有していた『借家権を承継』することができ、退去を拒むことができます。」
ケース2 「同様の前提で、相続人Cがいるケースでは、内縁の当事者の間には、
相続権がないので、Aが死亡した場合でも、BはAの有していた借家権を相続により
承継することはできませんが、Bは、Aの『相続人Cが相続により取得した借家権(注)
を援用』することにより、甲建物の所有者から の退去請求を拒むことができます。
(最判昭42.2.21)
(注)賃借人の死亡は賃貸借の終了事由ではないので、賃借人が死亡したときは、賃借権は
相続人承継されます。(民法896条)
また、相続人Cからの明渡請求、同居拒否等に対しては『権利濫用の法(民法1条3項)』
により対抗することができす。」 (最判昭39.10.13)
以上は、建物の賃借人と事実上の夫婦(内縁の当事者)又は養親子関係にある同居者を保護し、
借家権の承継を認めて「生活の基盤を確保」するためのものであります。
このような『内縁関係』として保護さるための『夫婦として実質』ありと認められるためには
(単に一緒に生活しているというだけでは足りず)、
① 婚姻の意思~両当事者が夫婦として生活する意思を持っていること
② (夫婦としての実態を伴った)共同生活~(一般的には)3年以上の継続的な期間が必要。
➂ 法律上の婚姻を妨げる障害がないこと。
④ 社会的認知~周囲から夫婦として認識されていること
が必要と言われています。
今回で、以上です。